家庭菜園を始めて早数年、一見カンタンそうに思えた土いじりも、いかにして畑を耕すかに始まり、また雑草や虫の問題など様々な事に直面し、およそ一筋縄ではいかないなと感じる今日この頃です。
だけど、自然を相手にする物事は総じて楽しい、とも感じますね。
そして今回は、そんな家庭菜園の問題の1つである農業用水の確保についてです。
畑の近くに水道が引かれていて自由に使える、と言う様な場所なら良いのですが、なかなかそう言った環境が少ないのが現実で、重いポリタンクなどで農業用水を運搬している人達にとってはちょい読みしたくなる内容となっております。

材料調達
上の写真は、近くの建材屋にて材料を調達しているところで、2m、1.5mの単管パイプや木材、単管同士を組み合わせるクランプと言う材料を購入しました。

ポリタンクの設置
場所を菜園に移しまして、農業用水を確保する為の大型のポリタンクの設置です。
このポリタンクは同じく菜園をやっている隣の家のオジサンにもらった物です。その容量はかなりのもので、ザッと100~300ℓ位はあるでしょうか(すみません…正確な数字は不明です)。
そして、そのまま置いただけでは水位が低い時などは水を汲みにくい事と、強風時の転倒防止の為にタンク上部が腰の高さ付近になる様、土に埋めて調整しました。

単管パイプを組む
設置したポリタンクに合わせ、単管パイプ、クランプを組み合わせていきます。
この際、下部のタンクに向かって上の単管パイプに下がり勾配(こうばい)をつける事がポイントです。 木材も、組んだ幅に合わせてノコギリで切り、設置しました。
勾配をつけるとは…ザックリ斜めにする、と言う事です。
ここまでの様子でお分かりの方も大分いらっしゃるかと思いますが、農業用水を自動的に確保するシステムなどと大袈裟な事を言って参りましたが、単純に降った雨水をタンクに流れ落ちる様にする仕組み、と言う事です。

そして調達へ
その日の夕方くらいには、丁度雨模様になってきました。
仕上げに波板(なみいた)と言う材料を上の写真の様にサイズを合わせてカットし、木材の部分にビス止めすれば、農業用水の確保システムの完成となります。
そして、今回は何故この様な仕組みを用いたかと言うと、例えばポリタンクをそのまま設置し、雨が1日中降り続いたとしても、雨水と言うのは意外と貯まらないものなんですよね…。(水を欲する気持ちに反する補正は多分にあるが)
そこで、この様に言わば小さい屋根を用いて雨水を集める事で、農業用水をより効率的に貯める事が可能になる、と言う訳ですね。
設置後の実感として、各季節の雨降りシーズン(梅雨や春雨、秋雨等)に貯まった雨水によって、家庭菜園に必要な水は十分に賄えております。
ワンポイントアドバイス
家庭菜園において、雨水をいかにして確保しておくかが、より良い栽培をするポイントです。
家庭菜園に関連する記事はこちら。家庭菜園の初心者にありがちな注意点まとめ
ブログ執筆中にも丁度雨が降ってきたので、どの位水が貯まっているか、ちょっと見てきます。


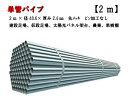




コメント